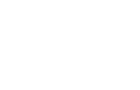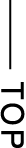なぜフリーターの就職は難しい?企業と本人目線から解説
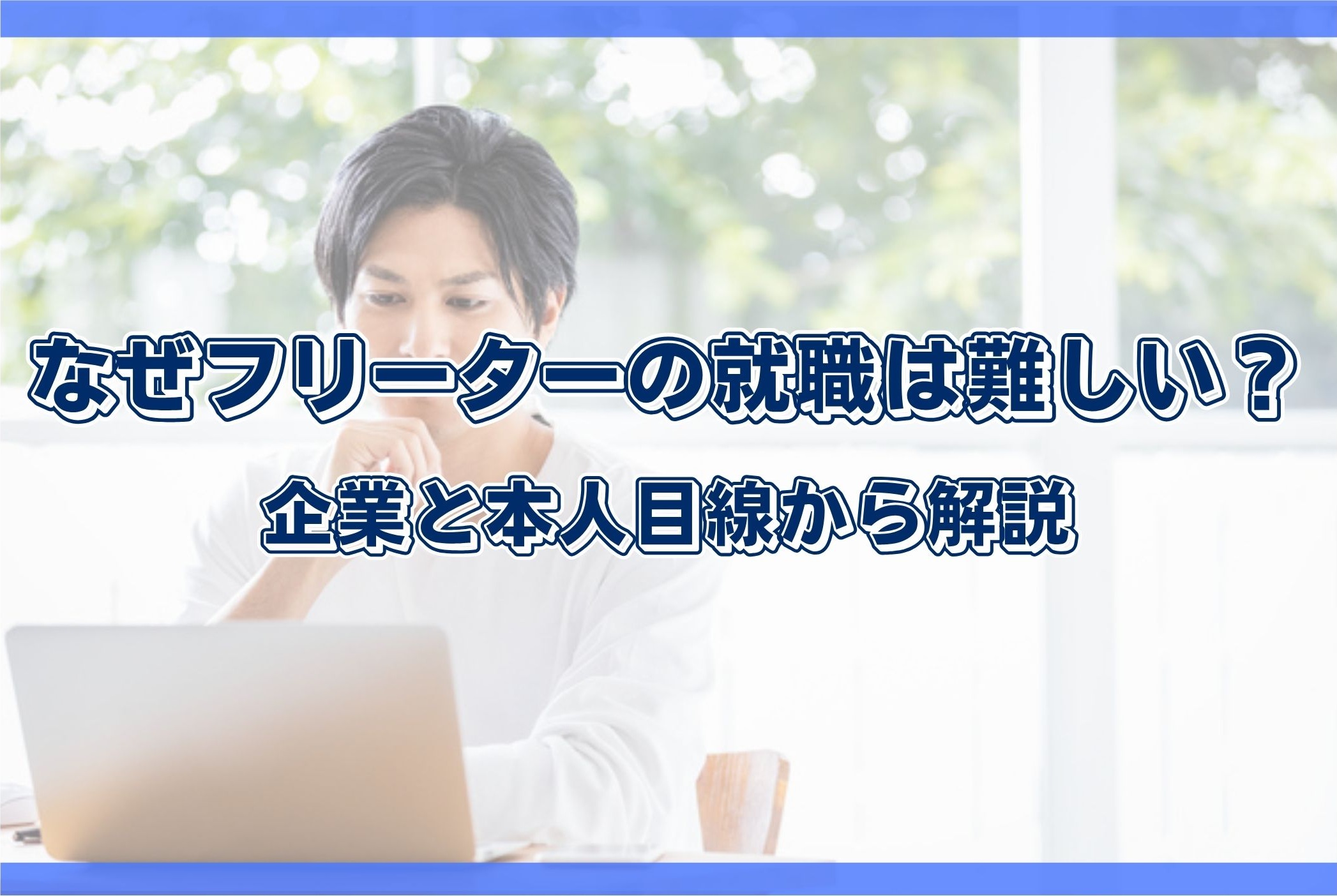
「頑張っているのに、なかなか書類選考を通過できない」
「面接でうまく自分をアピールできない」
フリーターからの就職活動が難航すると「自分には誇れる経験なんてない」と自信をなくしてしまうもの。
この記事では、なぜフリーターの就職が難しいのか、その原因を「企業側の視点」と「あなた自身の視点」の両方から深掘りします。
【この記事でわかること】
- 【企業視点】なぜフリーターからの就職が難しいのか?
- 【求職者視点】なぜフリーターからの就職が難しいのか?
- 企業からのネガティブイメージを払拭するには?
- フリーターが狙うべき職種の特徴
- 就活中に頼れるところ
- 正社員までをつなぐ!製造業・工場特化のHOPEエージェント
- まとめ
【企業視点】なぜフリーターからの就職が難しいのか?
フリーターから正社員への就職が「難しい」と言われるのには、いくつか理由があります。
まずは、採用担当者が懸念していることを知りましょう。
早期離職するのではないか
企業が採用活動にかけるコストと時間は、決して少なくありません。
求人広告の出稿、書類選考、複数回にわたる面接、そして採用後の研修。
一人の社員を迎え入れるために、多くの社員が時間と労力を費やしています。
だからこそ、企業が最も恐れることの一つが「早期離職」です。
採用担当者は、職歴を見て「これまで比較的自由な働き方をしてきた分、正社員としての責任や厳しいノルマ、人間関係のストレスに耐えられず、すぐに辞めてしまうのではないか」という懸念を抱きがち。
アルバイトの場合「この仕事は合わない」と感じれば、比較的簡単に辞めることができます。
しかし、正社員はそうはいきません。
企業としては「困難な状況でも、粘り強く業務に取り組んでくれる人材か」「長期的に会社に貢献してくれる人材か」という視点で厳しくチェックしています。
そのため、フリーター期間が長かったり、アルバイトの離職回数が多かったりすると、「忍耐力がない」「飽きっぽい」というネガティブな印象を与え、採用に慎重になってしまうのです。
働く意欲や責任感はあるのか
「なぜ正社員ではなく、フリーターという働き方を選んだのですか?」
これは、フリーターの就職活動で必ずと言っていいほど聞かれる質問です。
この質問に対しポジティブな理由を説明できない場合、企業は「働く意欲が低いのではないか」「責任のある立場を避けてきたのではないか」という疑念を抱きます。
正社員は、アルバイトに比べて大きな責任を負います。
自分の仕事が会社の業績に直結することも少なくありません。
一方で、アルバイトの業務は、比較的定型的で責任範囲が限定されていることが多いのが実情です。
そのため「より自由な時間を優先してきた」「プレッシャーのかかる仕事は避けたかった」という印象を与えてしまうと「重要な仕事を任せられない」「向上心がない」と判断されてしまいます。
企業は、給与を支払う以上、その対価として高いパフォーマンスと責任感を求めます。
フリーターという選択に明確な目的意識や将来のビジョンが感じられない場合「意欲や責任感が低い人材」と見なされ、採用候補から外されてしまう可能性が高まります。
ビジネススキルが不足していないか
新卒採用では社会人経験がないことが前提のため、ポテンシャルや人柄が重視されます。
一方で中途採用では、これまでの経験で培った「即戦力となるスキル」が求められます。
フリーターからの就職は、この「新卒」と「中途」のどちらの枠にも当てはまりにくいという難しさがあります。
企業が特に気にするビジネススキルは、以下のようなものです。
■基本的なビジネスマナー
正しい敬語の使い方、電話応対、ビジネスメールの作成、名刺交換など、社会人としての基礎的なマナーが身についていないのではないか。
■PCスキル
Wordでの文書作成、Excelでのデータ集計・分析、PowerPointでの資料作成など、多くの企業で必須となるPCスキルが実務レベルに達していないのではないか。
■論理的思考力・問題解決能力
指示された業務をこなすだけでなく、主体的に仕事を進めた経験が乏しいのではないか。
上記はOJTや研修制度が整っている新卒採用とは異なり「できていて当たり前」と見なされることが多いスキルです。
これらのスキル不足が懸念されると「入社後の教育コストがかかる」「成長に時間がかかる」と判断され、採用のハードルが上がってしまいます。
組織へ適応できるか
会社は、様々な年齢や役職、価値観を持つ人々が集まる「組織」です。
企業が円滑に事業を進めるためには、社員一人ひとりの協調性が不可欠。
採用担当者は、フリーターがこの組織の一員としてスムーズに溶け込めるかどうかを見ています。
特に、以下のような点が懸念されます。
■チームワークへの意識
アルバイト経験では、個人で完結する作業が中心だったかもしれません。
しかし、正社員の仕事は、チームで目標を達成することがほとんどです。
周囲と連携し、助け合いながら仕事を進めることができるか、という点に不安を持たれがちです。
■年齢とプライドの問題
フリーター期間が長いと、年下の社員が上司や先輩になるケースも珍しくありません。
その際に、変なプライドが邪魔をして、年下の上司からの指示を素直に受け入れられなかったり、年下の先輩から謙虚に仕事を学ぶ姿勢がなかったりするのではないか、と懸念されます。
■企業文化への適応
企業には、それぞれ独自のルールや価値観、いわゆる「企業文化」があります。
自由な働き方に慣れていると、企業の厳格なルールや独特の文化に馴染めず、ストレスを感じてしまうのではないか、と見られています。
このように、個人の能力が高くても組織の輪を乱す可能性のある人材は、敬遠される傾向にあるのです。
新卒至上主義
日本の雇用慣行として根強く残っているのが「新卒一括採用」の文化、いわゆる「新卒至上主義」です。
特に大手企業や歴史のある企業では、今もなおこの傾向が強く見られます。
新卒至上主義の企業では、社会人経験のない学生を「まっさらな状態」で採用し、自社の文化や仕事の進め方を一から叩き込んで、長期的に育成していくことを理想としています。
この採用方針では、大学卒業後すぐに就職しなかったフリーターは「決められたレールから外れた人材」と見なされてしまい、結果として就活のハードルが上がってしまうのです。
【求職者視点】なぜフリーターからの就職が難しいのか?
企業側の懸念だけでなく、求職者であるフリーター自身が就職活動でつまずきやすいポイントもあります。
就職活動の進め方がわからない
新卒であれば、大学のキャリアセンターが手厚くサポートしてくれ、周りにも同じように就職活動をする仲間がたくさんいます。
しかし、フリーターからの就職活動は、基本的には「たった一人」で進めなければなりません。
この孤独感が、まず最初の大きな壁となります。
「何から始めたらいいんだろう?」
「求人サイトはたくさんあるけど、どれを使えばいいの?」
「履歴書や職務経歴書の書き方がわからない…」
このように、具体的な行動を起こす前の段階で、何から手をつけていいかわからずに立ち止まってしまうケースは多いです。
新卒採用のように決まったスケジュールがないため「いつでも始められる」という安心感が、逆に行動を先延ばしにする原因にもなります。
また、相談できる相手がいないため、自己流で就職活動を進めてしまいがち。
自分に合った企業の探し方、効果的な応募書類の作成方法、面接対策のポイントなど正しい情報を得られないまま手探りで活動した結果、なかなか選考を通過できず、時間だけが過ぎていく…という悪循環に陥ってしまうのです。
自分に自信がない
フリーター期間が長くなるほど「正社員経験がない」という事実にコンプレックスを感じ、自分に自信をなくしてしまう人は少なくありません。
「自分にはアピールできるような立派なスキルも経験もない」
「同い年の友達は正社員として活躍しているのに、自分は…」
このように、周りと自分を比べて劣等感を抱いたり、アルバイト経験を「大したことではない」と過小評価してしまったりする傾向があります。この自信のなさは、就職活動のあらゆる場面でマイナスに作用します。
自信がないと、まず求人に応募する一歩が踏み出せません。「どうせ自分なんて採用されるはずがない」というネガティブな気持ちが先行し、魅力的な求人があっても「未経験者歓迎と書いてあるけど、きっと経験者が優先されるだろう」と諦めてしまうのです。
運良く面接に進めても、自信のなさは態度や表情に表れ、面接官に「頼りない」「覇気がない」という印象を与えてしまいます。経歴に対する負い目から、声が小さくなったり、視線が泳いだりして、本来持っているはずの魅力さえも伝えきれなくなってしまうのです。
面接でのアピールができていない
就職活動の最大の関門である面接。
本人自身が経験や意欲をうまくアピールできずに、お見送りになってしまうケースが後を絶ちません。
その背景には、以下のような準備不足があります。
フリーター期間についての説明がネガティブ
「なぜフリーターをしていたのですか?」という質問は、ほぼ確実に聞かれます。
これに対して「特に目的はなく、なんとなく…」「正社員は大変そうだったので」といった正直すぎる、あるいは後ろ向きな回答をしてしまうと、働く意欲や計画性のなさを露呈すること。
たとえ事実であったとしても、フリーター経験から何を学び、それが今後どう活かせるのか、というポジティブな視点で語る準備ができていないのです。
志望動機が「自分本位」になっている
「安定したいから」「正社員になりたいから」という気持ちは、就職を目指す上で当然の動機です。
しかし、それだけを伝えても、採用担当者には響きません。
企業は「なぜ他の会社ではなく、うちの会社を志望するのか」を知りたいのです。
業界研究や企業研究が不足しているため「この会社で何がしたいのか」「どう貢献できるのか」という具体的なビジョンを語れず、「どこでもいいのでは?」という印象を与えてしまいます。
アルバイト経験を具体的に語れない
「アルバイト経験で何を学びましたか?」と問われ「接客を頑張りました」「チームワークを大切にしました」といった抽象的な答えで終わってしまうのも、よくある失敗例です。
「お客様の年齢層に合わせて声のトーンや話題を変える工夫をした結果、リピート率が〇%上がった」「新人アルバイトの教育係としてマニュアルを作成し、全体の業務効率を改善した」というように具体的なエピソードや数字を交えて、自分の強みと結びつけてアピールする必要があります。
企業からのネガティブイメージを払拭するには?
企業からのネガティブイメージを払拭して「この人を採用したい」と思わせるためには「過去の経験や今の姿勢を、企業が求める言葉に変換して伝える」ことが大切。
面接や書類選考では、以下の3つのポイントを意識しましょう。
フリーターだった理由はポジティブに説明する
「なんとなく」「やりたいことがなかった」といった曖昧な返答は避け、具体的でポジティブな理由を述べましょう。
例えば「資格取得のため」「専門スキルを磨くため」「家業の手伝いのため」などの前向きな理由や、やむを得ない事情があった場合は簡潔に伝えます。
この際、決して過去の選択を後悔しているようなネガティブな発言は避けましょう。
正社員になりたい理由を明確に説明する
正社員になりたい理由は「安定したいから」だけでなく「この企業で、この仕事を通じて、どのように貢献したいのか」という視点で具体的に語れるようにしましょう。
例えば「アルバイトでは経験できない責任ある仕事に挑戦したい」「チームで協力して大きな目標を達成したい」「御社の〇〇という事業に魅力を感じ、〇〇のスキルを活かして貢献したい」など、企業への熱意と仕事への意欲を伝えることがとても大事です。
アルバイト経験を「ビジネス言語」に翻訳する
「アルバイト経験なんて、大したアピールにならない」と思い込んではいけません。
どんな仕事にも、正社員として通用するスキルや経験が隠されているからです。
その価値を「ビジネス言語」に翻訳して伝えましょう。
■居酒屋のホール担当
「常に複数のお客様の状況を把握し、注文や配膳の優先順位を判断するマルチタスク能力を培いました。
クレーム対応では、まずお客様のお話を丁寧に伺う傾聴力を活かし、店長に的確に状況を報告することで、迅速な解決に繋げました。」
■アパレルの販売員
「月間の売上目標を達成するため、お客様との会話からニーズを汲み取り、+1点の購入に繋がる提案力を磨きました。結果として、担当月の個人売上目標を3ヶ月連続で達成しました。」
■コンビニのスタッフ
「新人スタッフの教育係を任され、独自のチェックリストを作成して指導にあたりました。その結果、新人が一人でレジ対応できるようになるまでの期間を平均2日間短縮することに成功し、育成能力と課題解決能力を学びました。」
「何をしていたか」だけでなく「その経験から何を学び、どう成果を出したか」を具体的に語ることで、あなたの経歴やビジネススキルを証明できます。
社会人としてのマナーや常識を身につける
基本的なことですが、これができていないと第一印象で大きく損をしてしまいます。
■言葉遣い、身だしなみ
面接での敬語、清潔感のある服装や髪型は基本中の基本です。
■報連相(報告・連絡・相談)の意識
アルバイトで上司や同僚との連携をどのように行っていたか具体的に説明できると、組織への適応能力があることをアピールできます。
■時間厳守
遅刻は厳禁。面接だけでなく、書類提出の期限なども必ず守りましょう。
フリーターが狙うべき職種の特徴
未経験歓迎求人が多い
一番のポイントは、未経験を前提に採用している職種を狙うこと。
企業側も「育てながら戦力にしていく」というスタンスで募集しているから、経験やスキルに自信がなくてもチャレンジしやすいです。
例としては、以下のような職種です。
■営業職(特に法人営業やルート営業)
■接客・販売職(アパレル、家電、飲食など)
■コールセンター・カスタマーサポート
■介護職員
■物流・倉庫管理
■製造業・工場の作業スタッフ
人手不足
もうひとつの狙い目は、慢性的に人材不足の業界や職種。
人手が足りていない=採用ハードルが下がっている=未経験でも受かりやすい、という構造になっています。
特に以下の分野は、常に求人が出ている傾向が強いです。
■介護業界
■飲食業界
■建設・運輸・物流
■製造業・工場
■IT業界の一部(エンジニアアシスタントやヘルプデスクなど)
自分のアルバイト先
意外と見落としがちですが、今働いているアルバイト先から正社員を目指すのも堅実なルートです。
なぜかというと、以下のように仕事ぶりを知っているから。
■すでに業務を理解している
■職場の人間関係ができている
■働きぶりが評価されやすい
飲食店やコンビニ、ドラッグストア、アパレルなどでは「社員登用制度」が用意されているケースもあるため、まずは店長や上司に相談してみるといいかもしれません。
もし正社員募集をしていなかったとしても、「希望があるなら考える」と言ってもらえる可能性もあります。
就活中に頼れるところ
就活中のサポート機関について、特に使いやすい3つの窓口を紹介します。
1. ハローワーク
定番中の定番ですが、やっぱり心強い存在です。
ハローワーク(公共職業安定所)は全国各地にあり、無料で使えるのがメリット。
履歴書の書き方から求人紹介、職業訓練の案内など幅広く対応してくれます。
また、最近は「若年者向け支援窓口」や「専門相談員」など、20〜30代の未経験者をサポートする体制も整っているところも。
「とりあえず相談してみたい」だけでもOKです。
2. ジョブカフェやサポステ
ハローワークよりもカジュアルに相談したい人には、ジョブカフェ(若年者の就職支援施設)やサポステ(地域若者サポートステーション)もおすすめです。
どちらも、若者の「働くまで」をサポートするための公的機関で、全国各地に拠点があります。
・自己分析や適職診断
・就労体験(職場体験的なもの)
・就活セミナーや面接練習
・専門スタッフとの個別面談
こういった支援が無料で受けられるため「就活の相談がしたい」という人にもぴったり。
場所によって雰囲気も違うので、ホームページなどで近くの施設をチェックしてみてください。
3. 転職エージェント
「正社員を目指したい」「具体的な求人を紹介してほしい」という場合は、民間の転職エージェントも心強い味方。
転職エージェントは、専任の担当者(キャリアアドバイザー)がついて、希望に合った求人を探してくれたり、面接日程の調整・選考対策などもフォローしてくれるサービスです。
「経験者向け」のイメージがあるかもしれませんが、最近はフリーターや未経験者向けのエージェントも増えてきています。
エージェント側も「あなたに就職してもらうこと」で報酬が出る仕組みなので、親身になって動いてくれるケースが多いです。
正社員までをつなぐ!製造業・工場特化のHOPEエージェント
「正社員として働きたいけど、なかなか決まらない」
そんなときは、正社員にこだわりすぎず、派遣を「つなぎ」にするのもひとつの手。
製造業や工場系の仕事には、まずは派遣で現場経験を積んでから、ゆくゆくは正社員登用につながるケースも少なくありません。
「働きながらスキルをつけたい」「いきなり正社員はちょっと不安」という人におすすめしたい選択肢です。
そこで心強い味方になってくれるのが、製造業・工場に特化した人材エージェント『HOPE.AGENT』。
\ HOPE.AGENTの特徴 /
◎ 取り扱い求人は製造業に特化、常時1,000件以上!
◎ 専属エージェントがワンストップサポート(相談、求人紹介、履歴書の添削・面接対策・キャリアチェンジまで)
◎ 年間800人以上をサポートしてきた実績あり
◎ 身だしなみや言葉遣い、ビジネスマナーのレクチャーあり
◎ 仕事内容が合わなかった場合は、別のお仕事をご案内可能
HOPE.AGENTは「求人を紹介して終わり」ではありません。
身だしなみや言葉遣いといった社会人スキルの底上げ、ワンストップの就職サポートなど徹底したフォローに自信があります。
職歴が浅い、未経験、異業種からのチャレンジなど様々な背景を持った方たちの人生に向き合ってきました。
新しい一歩を踏み出すときに感じる不安や迷い、そんな気持ちはぜひHOPE.AGENTへご相談ください。
★━━━━━━━━━━━━━━…
…━━━━━━━━━━━━━━━━★
まとめ
フリーターからの就職が難しいと言われる背景には、企業側の不安(早期離職・ビジネスマナー・責任感の有無)と、求職者側のつまずき(就活の進め方・自信のなさ・面接でのアピール不足)があります。
逆に言えば、「その不安をどう払拭するか」「どう準備すれば伝わるか」が見えてくれば、対策は可能です。
■フリーターだった理由は、前向きに説明できるようにする
■正社員として働きたい理由を、企業視点で伝える
■アルバイトでの経験は「ビジネススキル」に言い換えて語る
この3つを意識するだけでも、面接での印象は大きく変わります。
また、未経験歓迎の職種を狙ったり、エージェントや公的機関をうまく活用することで、就職活動を前進させられるはずです。