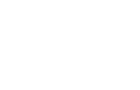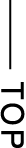新卒ですぐ辞めたらどうなる?再就職へ向けて知っておきたいこと
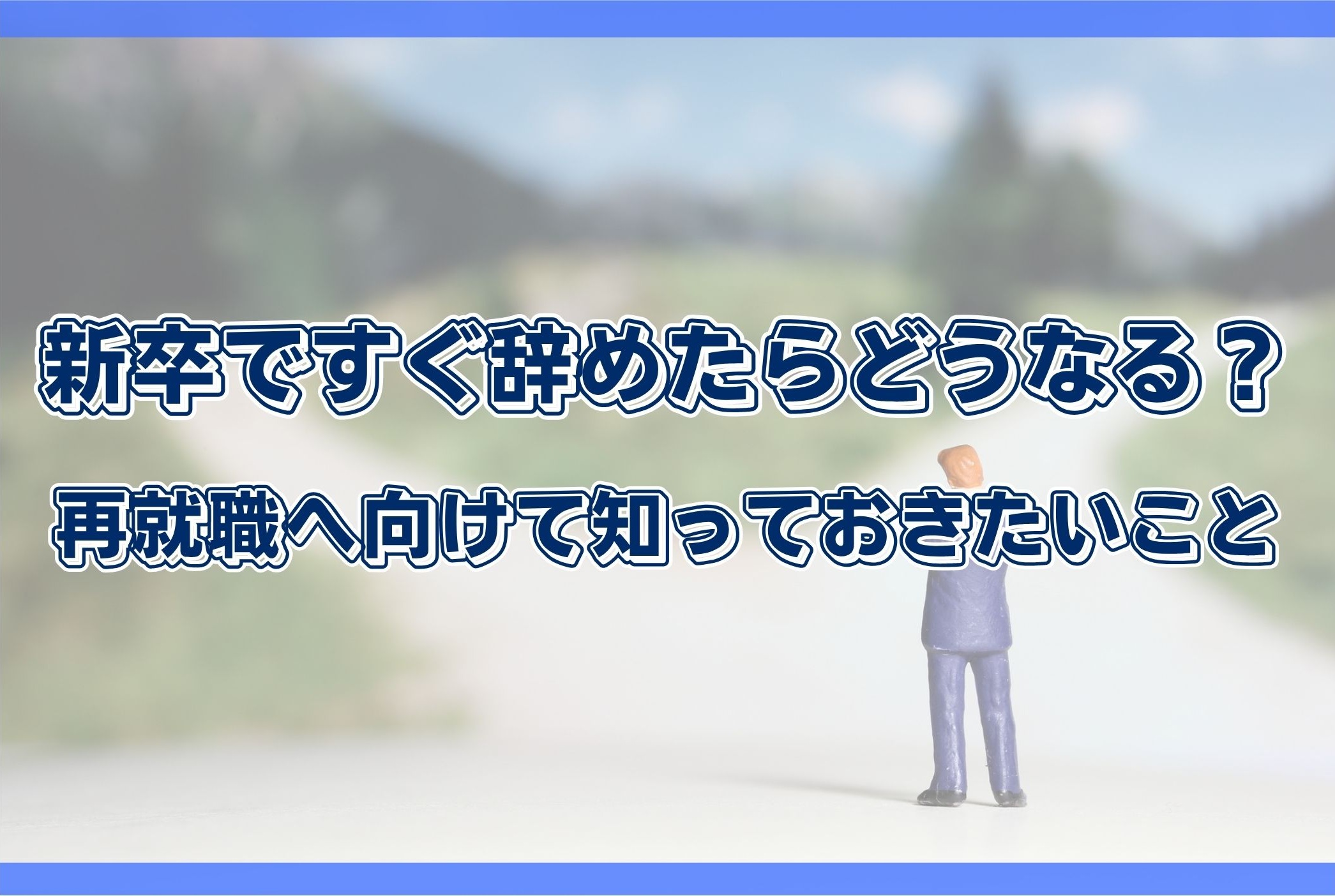
「新卒で入った会社をすぐ辞めるなんて、自分はダメなのかな……」
そんなふうに悩んでいる人へ。
結論から言えば、新卒の早期退職は珍しくないし、終わりでもありません。
むしろ「ここで辞めることが、人生を立て直す一歩になる」という捉え方もできます。
とはいえ、実際に辞めたあとの再就職やキャリア形成には注意点もあるし、不安になるのも当然なこと。
この記事では、新卒で退職を考えている方へ向けて、辞めたあとにどうなるのか、退職の仕方、再就職に向けて知っておきたいことを解説します。
【この記事でわかること】
- 新卒1年以内の離職率
- 新卒ですぐ辞めたらどうなるのか
- 新卒が退職を考える理由
- 早期退職の影響(良い面と悪い面)
- 退職したいと思ったらやるべきこと
- 早期離職を繰り返さないために考えること
- 再就職先が見つからないとき
- 次の仕事が見つかるまで!製造業特化のHOPEエージェント
- まとめ
新卒の早期離職は珍しくない
厚生労働省によると、学歴別に見る新卒の1年目での離職率は以下のとおり。
■中学卒:31.4%
■高校卒:16.7%
■短大卒:18.5%
■大学卒:12.3%
離職率が最も高い中学卒だと新卒の約3人に一人、最も低い大学卒でも約8人に一人が1年目で退職しています。
このことから、新卒だとしても早期離職する人はしますし、そこまで珍しくはないことが伺えます。
※参照元:新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します
新卒ですぐ辞めたらどうなる?
新卒で入社してすぐに辞めた場合、気になるのが「その後どうなるのか?」という点。
結論から言うと「すぐ辞めたから終わり」ではありません。
ただし、転職市場での立ち位置や見られ方にはちょっとした違いが出てくるので順に説明します。
「第二新卒」として扱われる
基本的に、新卒で入社してから3年以内に転職する人は「第二新卒」として扱われます。
「第二新卒」とは「学校卒業後、1〜3年以内に就職したけど早期離職して転職活動している人」を指します。
卒業時の年齢にもよりますが、20代前半〜半ばが中心層。
入社して1ヶ月や3ヶ月で辞めたとしても「3年以内」なら該当します。
実際に第二新卒向けの求人もたくさんありますし、企業側も「一社目ミスマッチだったのかな」と理解してくれるところも増えています。
「新卒」との違い
新卒は「就職活動したことがなく、初めて社会に出る人」。
そのため企業側は、ビジネスマナーや仕事の基本をイチから教えることや、ポテンシャル採用を前提としています。
一方、第二新卒は「すでに社会に出て、一度就職した人」。
「基本的な社会人経験が少しある」「前職でのギャップを乗り越えた経験がある」と見なされやすい傾向にあります。
「既卒」との違い
既卒とは「卒業後、一度も正社員として働いたことがない人」を指します。
つまり「就職せずにフリーターや無職だった人」や「就職浪人していた人」が該当。
第二新卒との大きな違いは「正社員経験の有無」にあります。
既卒は社会人経験がほぼゼロと見なされることが多いですが、第二新卒は「短期間でも社会で働いた経験がある」点が評価されます。
新卒が退職を考える理由
仕事にやりがいを感じられない
新卒が退職を考える大きな理由のひとつが「やりがいの欠如」。
学生時代は「社会人になれば成長できる」「何かを成し遂げたい」と期待を抱いて入社しますが、実際の業務は地味な作業の繰り返しだったり、目に見える成果が出にくかったりしてモチベーションを保てなくなります。
特に成長意欲の高い人ほど自分のスキルが活かせない・伸びない環境に不安を覚えやすいとも言えるでしょう。
また「この仕事を通じて誰の役に立っているのか」「社会的な意味があるのか」が見えにくいと、存在意義を感じられず心が折れてしまうことも。
「やりがい」は抽象的な概念ですが、ここを満たせないと離職につながりやすいです。
残業が多すぎる
定時で帰れると思っていたのに、実際は毎日終電ギリギリ。
そんな日々が続けば、体力的にも精神的にも限界がきます。
学生時代には経験のなかった慢性的な疲労や時間のなさに、新卒であれば戸惑いや不満を抱いても当然。
また「なぜこんなに働いてるのか」「この働き方に意味はあるのか」と疑問を感じ始めると、モチベーションが一気に下がってしまいます。
特に近年は「ワークライフバランス」や「自分らしい生き方」を重視する価値観が広がっているため「働きすぎる会社=ブラック」と見なされ、早期退職を選ぶきっかけになりやすいです。
人間関係が悪い
職場の人間関係は、仕事内容以上に新卒のメンタルに影響を与えるポイント。
上司や先輩が高圧的だったり、話しかけにくかったりすると「質問しづらい」「失敗が怖い」と感じて萎縮してしまいます。
特に新卒はまだ社会人としての基礎も整っていないため、サポートや安心感を得られないと孤独を感じやすいもの。
周囲との信頼関係が築けないまま日々の業務に追われると「自分はここにいていいのか?」という不安に発展し、退職を選ぶことも。
人間関係のストレスは、業務内容以上に「会社に居続けることのハードル」を高くしてしまうと言っても過言ではありません。
会社の将来性が不安
経営方針が見えない、売上が下がっている、社員の入れ替わりが激しい。
そんな状況を見ると「この会社に未来はあるのか?」と新卒でも敏感に察知します。
特に情報感度が高く、転職市場にも詳しい層は「今ここにいて大丈夫?」という危機感から早めに次の選択肢を模索し始めることも。
自分の成長やキャリア形成を真剣に考えている人ほど「今の環境で得られるものが少ない」と感じたら、見切りをつけるのが早いです。
将来のビジョンを語れない会社に対しては、不安よりも「無関心」が強まり、結果として離職という選択につながります。
新卒が早期離職を考える理由を総括すると入社前と入社後の「ギャップの大きさ」が背景にあります。
説明会や面接で見た会社の姿と、実際に入社して経験する現場のリアルとの乖離。
そのギャップが仕事・労働時間・人間関係・将来性、どの観点であっても「想定外」として積み重なることで、「ここじゃないかも」という違和感が強くなります。
そして、それが限界を超えたときに「辞める」という選択肢が現実味を帯びてきます。
企業側としては、新卒の早期離職は単なるわがままではなく「期待していた未来が崩れたサイン」と捉える視点も大事かもしれません。
早期退職の影響は?良い面と悪い面
【良い面】ストレスから解放される
合わない職場で働き続けることは、心身に大きな負担をかけるものです。
人間関係に悩み、業務が苦痛で、出社するたびに胃が痛くなる──そんな状態が続けば、メンタルヘルスを崩すリスクは高まる一方。
早期退職によってそのストレス源から距離を置けるのは、自分を守る方法のひとつ。
特に新卒の場合、社会人経験が浅いために「これが普通なのかな」と無理をしがち。
でも、つらさを我慢し続けて働くことが必ずしも正解とは限りません。
むしろ早い段階で環境をリセットすることで、自分らしく働ける道を探し直すきっかけにもなるのです。
【良い面】今より良い職場へ転職できる可能性
早期退職はネガティブに捉えられがちですが、それによって新しい道が開けることも事実です。
もっと自分の興味に近い業界に挑戦したり、価値観が合う企業に出会えたりするチャンスが広がっています。
最近では「キャリアの軸を見直した上での転職」だと評価してくれる企業も増えてきていて、早期離職=マイナスではなくなりつつある。
もちろん、次を選ぶときは慎重に情報を集めたり、自分自身を客観的に振り返ったりする必要がありますが、「合わない場所に居続ける」より「フィットする職場に移る」ことを選ぶのは、結果的に本人にとっても会社にとっても健全な選択です。
【悪い面】次の職場では「新卒」とみなされない
先述しましたが、新卒で早期退職をするとその後の転職先では「既卒」や「第二新卒」として扱われます。
企業によっては「新卒枠」の研修制度や手厚いサポートを受けられなくなることもあり、スタート地点がやや不利になる可能性も。
たとえば「新卒限定の総合職採用」などの枠には応募できなくなったり、ポテンシャルよりもスキルや即戦力性を重視されたりするケースもあります。
また、面接の場では「なぜ辞めたのか」という理由を深掘りされると思っておきましょう。
その際、ただ「職場が合わなかった」と答えるだけでは、熱意や責任感を疑われてしまうことも。
短期間でも一度社会に出たからこそ、「自分は何がしたいのか」「どんな環境が合うのか」をきちんと言語化することが、次の選考では重要になってきます。
【悪い面】転職活動自体が大変
退職を決めたあと、すぐに希望通りの仕事が見つかるとは限りません。
早期退職の場合、実務経験が浅いため応募できる求人の選択肢が限られることもあるでしょう。
特に「とりあえず辞めてから考える」というスタンスだと、収入がない状態での就職活動になり、精神的にも金銭的にもプレッシャーがかかりやすいので要注意です。
また、周囲からの目が気になったり、自分の決断が正しかったのか悩んだりする場面もあるかもしれません。
情報収集、企業分析、履歴書や職務経歴書の準備、面接対策など、やるべきことも多く、エネルギーが必要。
だからこそ「辞めて終わり」ではなく「その先どう動くか」までセットで考えることが、早期退職をポジティブな転機に変えるポイントです。
退職したいと思ったらやるべきこと
1. 一度自分の気持ちを整理する
退職したいと衝動的に思っても、いきなり「辞めます!」と伝えるのは一旦ストップ。
まずは、自分の気持ちを整理する「作戦タイム」を取りましょう。
■なぜ辞めたいのか?
■何がつらいのか?
■次にやりたいことは何か?
これを紙に書き出すだけでも、気持ちが落ち着いて冷静になれます。
感情だけで突っ走ると「辞めたあとどうしよう…」と焦る原因になりがちなので、一旦落ち着いて深呼吸しましょう。
作戦タイムを経て「やっぱり辞めるべきだ」と自分の中で腹が決まったら、次の行動フェーズに移りましょう。
2. 退職までのスケジュールを立てる
退職は、単に退職届を出せば終わりではありません。
引き継ぎや書類手続き、上司との面談など意外とやることが多いのです。
以下のように「いつ退職するか」「いつ伝えるか」のスケジュールをざっくり立ててみましょう。
■今月中に退職の相談をする
■来月末までに引き継ぎを終える
■その間に転職準備も始める
このとき気を付けたいのが、退職の申し出は就業規則に記載がある期間に行うこと。
法律上は「2週間前までに」伝えればOKですが、実際には会社の就業規則で「1ヶ月前」といったように、早めに設けられていることがほとんどです。
これは、突然抜けられると人的リソースの調整や社内での引継ぎが間に合わない可能性があるため。
法律上は2週間前だからといっても、円満に退職するためにも会社の就業規則に則って伝えることがスマートです。
3. 上司に退職の意思を伝える
退職を決めたら、いよいよ上司に伝えるタイミングです。
ここが一番緊張するシーンですが、ここを越えないと前には進めません。
まずは、いきなり本題に入らず「一度お話ししたいことがありまして…」とアポをとることから始めましょう。
対面またはWeb会議など、ちゃんと話せる場を用意してもらうのが基本です。
話すときは、以下の3つを意識しましょう。
■結論から先に伝える
「突然で申し訳ありませんが、退職を考えておりまして…」と、はじめに退職の意思を伝えましょう。
まわりくどい言い方だと上司も構えてしまうので、最初に結論を置くことで話が進みやすくなります。
■理由は「本音ベース+前向き変換」で伝える
退職理由として「上司と合わない」「毎日しんどすぎてもう限界」というのが本音だったとします。
そのまま感情むき出しで伝えると、上司との関係が一気に悪くなったり、引き止められたときに対話がしづらくなったりする可能性も。
それだと自分のためにならないですし、退職をスムーズに進める上でもハードルが上がってしまいます。
だからこそ「本音をまるごとぶつける」というよりも「自分の意思」に変換して、相手にも伝わる形で届けましょう。
たとえば、本音はこんなふうに変換できます。
「人間関係がつらい」
→ 「職場の人間関係も含めて、自分が心地よく働ける環境って何なのか、考え直す時間が必要だと思った」
「仕事が向いてなさすぎた」
→ 「今の仕事を通じて、自分がどんな働き方・役割に向いているのかを考え直す機会になった」
「上司と価値観が合わなかった」
→ 「自分にとって大事にしたい働き方や価値観がはっきりしてきて、それを軸に次のステップに進みたいと思った」
ポイントは本音の背景を含めつつ、相手が受け止めやすい言葉に変換すること。
「責める言葉」を使わない工夫が、自分自身を守ってくれます。
■感謝の気持ちを忘れずに
退職理由がなんであれ、在籍中にお世話になったのは事実。
最後に「これまでサポートいただいたことに感謝しています」と一言伝えるだけで、印象は大きく変わります。
「辞める=関係を切る」ではなく、「丁寧に次へ進む」ためのマナーとして、大事にしたい部分です。
4. お金と転職の準備を同時に進める
退職後、すぐに次の仕事が見つかるとは限りません。
そのため、もし「少し休んでから考えたい」場合でも生活費の計画は立てておきましょう。
■貯金はどれくらいあるのか
■家賃・食費・保険料の見通しはあるのか
■失業保険は使えるか
それと同時に、自己分析や転職サイト登録も始めましょう。
動き出すのは早い方が、焦らず選べるはずです。
5. それでもまだ迷ったら
「辞めるって決めたけど、本当にこれでいいのかな」と迷うのはごく自然なこと。
そういうときは、信頼できる先輩やキャリア相談の窓口、あるいはプロの転職エージェントに話を聞いてもらいましょう。
一人でぐるぐる考えるより、誰かに言葉にして話すことで頭が整理されます。
早期離職を繰り返さないために考えること
退職した原因を言語化する
早期離職を一度経験したあとに大切なのは「なぜ自分は辞めることを選んだのか」をきちんと振り返ること。
そのとき感じた違和感やストレスを曖昧なままにせず、具体的な言葉にして整理しておくことで、次の職場選びの判断基準がはっきりしてきます。
たとえば、「人間関係が合わなかった」とひとことで言っても、それは上司との相性なのか、体育会系の文化なのか、孤立しやすい環境だったのかによって、意味合いがまったく変わってきます。
同じように「やりがいを感じなかった」と思ったなら、それは業務の内容に問題があったのか、それとも評価制度や目標の立て方に納得感がなかったのかを深掘りしてみましょう。
退職理由をぼかさずに掘り下げることで「次はこういう会社は避けたい」「こういう価値観の環境なら働けるかも」と、自分にとっての「NG」と「希望」が見えてくるはずです。
これは面接対策にもつながりますし、同じ理由で再び離職しないための予防にもなります。
自己分析で自分を見つめ直す
原因を言語化したら、次は「自分ってどういう人間なんだっけ?」と改めて向き合う時間を設けましょう。
自己分析というと就活っぽいイメージがあるかもしれませんが、社会人になった今だからこそ見えてくる「リアルな自分像」もあるはずです。
実際に働いてみて初めてわかった強み・弱みや、向いている業務のタイプ、人との関わり方の好みなど、社会に出る前には気づけなかった部分も多いもの。
たとえば「正解が決まっている作業の方が落ち着く」とか「一人で完結するよりチームで進める方が得意」といった実感ベースの気づきは、自己理解において重要なヒントになります。
また、仕事に対する価値観、たとえば「成長できる環境を優先したい」「安定よりも自由な働き方がいい」なども改めて見直すことでキャリアの軸が定まりやすくなります。
この「自分を知る」プロセスができていないと、なんとなく雰囲気や条件だけで職場を選び、またミスマッチを起こしてしまうリスクあり。
だからこそ、少し時間がかかっても、ここは丁寧に向き合っておくことをおすすめします。
企業分析で自分とのマッチ度を分析する
自己分析ができたら、次は企業分析の番です。
求人票の条件だけではなく「この会社はどんな人を求めているか」「どんな文化や価値観が根付いているか」を読み解く力が求められます。
たとえば、ベンチャー企業ならスピード感や自主性が求められる一方で、大企業は役割が細かく分かれていて、調整力や根回しが重視されることもあります。
同じ「営業職」でも、個人向けと法人向けでは業務のスタイルがまったく違いますし、「風通しが良い」という言葉も会社によって意味が違ってきます。
だからこそ、企業のWebサイトや社員インタビュー、口コミサイトなどを活用してできるだけ多角的に情報を集めましょう。
また、説明会や面接での社員の話し方や雰囲気、質問への対応の仕方も企業文化を感じ取るヒントになります。
大事なのは「この会社に入れるかどうか」ではなく、「自分がこの会社で心地よく働けるかどうか」という視点で見極めること。
そのマッチ度を見誤ると、また同じような理由で短期離職を繰り返すことになりかねません。
事前にじっくり見比べる時間を持つことが、未来の自分を助ける選択につながります。
再就職先が見つからない?派遣やアルバイトも視野に入れよう
新卒で退職したあと「早く正社員として次を決めなきゃ」と焦ってしまう人は多いです。
もちろん、正社員として安定した職場を目指すことは悪いことではありません。
ですが「今すぐ正社員にならなきゃいけない」というプレッシャーを、自分にかけすぎないであげてください。
もし再就職先がすぐに見つからなかったとしても、それはダメなことでも「終わり」でもありません。
むしろ、派遣やアルバイトなど柔軟な働き方を一度挟むことは、キャリアのリズムを整える良い選択肢になります。
■派遣で事務職を経験しながら、自分の得意不得意を整理する
■アルバイトで生活費を確保しながら、転職活動にじっくり取り組む
■短期の仕事を通じて、社会との接点やリズムを保ち続ける
こうした選択は「逃げ」ではなく「地に足をつけたキャリア戦略」。
正社員以外の働き方を選ぶことで、かえって自分に合う業界や職種が見えてくることもあるはずです。
何より大切なのは「働いていない自分=価値がない」と思い込まないこと。
少し遠回りに見えても、自分を大切にできるルートを選んでも良いのです。
それが、結果的に次の正社員のチャンスにちゃんとつながっていくからです。
次の仕事が見つかるまで!製造業特化のHOPEエージェント
先述したように、正社員にこだわりすぎず派遣を「つなぎ」にするのもひとつの手です。
製造業や工場系の仕事には、未経験・フリーター歓迎など入口が広い求人が多数。
まずは派遣で現場経験を積んでから、ゆくゆくは正社員登用につながるケースも少なくありません。
「働きながらスキルをつけたい」「いきなり正社員はちょっと不安」という人におすすめしたい選択肢です。
そこで心強い味方になってくれるのが、製造業・工場に特化した人材エージェント『HOPE.AGENT』。
\ HOPE.AGENTの特徴 /
◎ 取り扱い求人は製造業に特化、常時1,000件以上!
◎ 専属エージェントがワンストップサポート(相談、求人紹介、履歴書の添削・面接対策・キャリアチェンジまで)
◎ 年間800人以上をサポートしてきた実績あり
◎ 身だしなみや言葉遣い、ビジネスマナーのレクチャーあり
◎ 仕事内容が合わなかった場合は、別のお仕事をご案内可能
HOPE.AGENTは「求人を紹介して終わり」ではありません。
身だしなみや言葉遣いといった社会人スキルの底上げ、ワンストップの就職サポートなど徹底したフォローに自信があります。
職歴が浅い、未経験、異業種からのチャレンジなど様々な背景を持った方たちの人生に向き合ってきました。
新しい一歩を踏み出すときに感じる不安や迷い、そんな気持ちはぜひHOPE.AGENTへご相談ください。
★━━━━━━━━━━━━━━…
…━━━━━━━━━━━━━━━━★
まとめ
■新卒の早期離職は、意外と珍しくない
実際の離職率データを見ても、1年以内に辞める人はそれなりにいる
■「第二新卒」として再スタートできる
すぐ辞めた=キャリア終了ではなく、今は「第二新卒」向けの求人やサポートも豊富
■早期退職にはメリット・デメリットがある
無理して働き続けるより、自分に合う環境を見つける方が長い目で見るとプラス
ただし、転職活動は準備が大事。辞めた理由や自分の強みをしっかり言語化すること
■焦らず、自分を見つめ直す時間を作ることが大切
再就職がすぐ決まらなくても大丈夫。派遣やアルバイトで経験を積むのもアリ
■プロのサポートも活用しよう
自分一人で抱え込まず、キャリアエージェントや相談窓口も頼ってOK