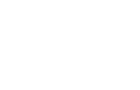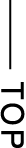「一生フリーターでいたい…なんとかなる?」将来への不安と向き合おう
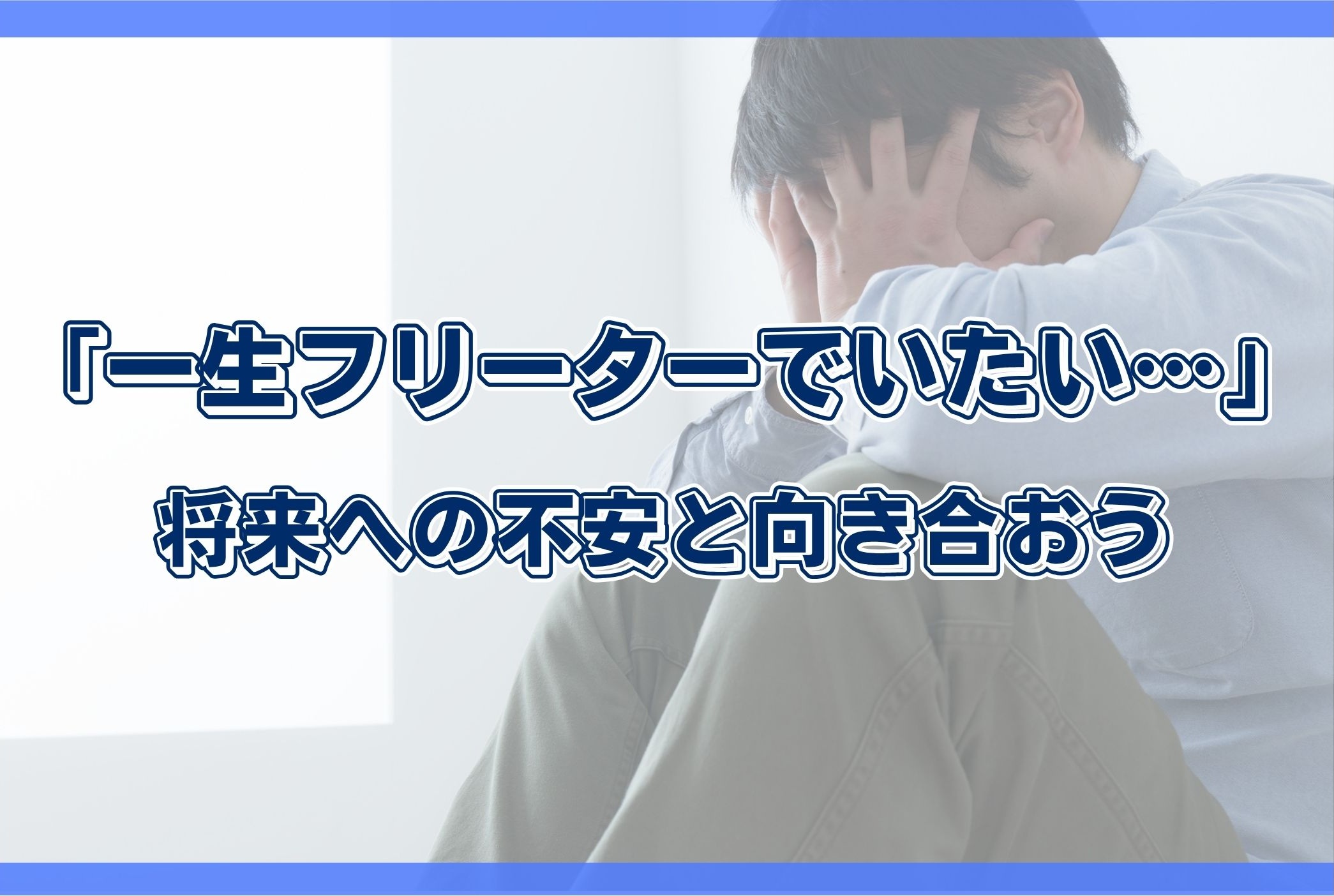
「このままずっとフリーターでも、なんとかなる?」
自由な時間、自分のペース、面倒な人間関係も最小限。
フリーター生活の気楽さに魅力を感じている人は少なくないはず。
その一方で、「将来大丈夫かな?」「親や周りからの目が気になる…」「年を取ってから困らないかな?」という不安が頭をよぎる瞬間もあると思います。
この記事では、フリーターでいることのメリットと将来性、その両方について考えてみました。
【この記事でわかること】
- そもそもフリーターとは?
- フリーターでいることの何が悪い?そのリスクやデメリット
- それでもフリーターでいたい!メリットと心理
- どんな人なら一生フリーターでいられる?
- 将来が不安なことも本音…正社員になるメリットは?
- フリーターから脱却するとしたら?
- 未経験歓迎求人多数!製造業・工場特化のHOPEエージェント
- まとめ
そもそもフリーターとは?
フリーターの定義
「フリーター」という言葉は日常的によく使われていますが、実は明確な定義はありません。
ここでは便宜上、総務省統計局が行った「労働力調査」での定義を見てみましょう。
フリーターの定義(狭義)
■年齢:15~34歳
■男性:学校卒業者
■女性:学校卒業者かつ未婚
■以下いずれかに該当する
・現在パート・アルバイトとして働いている人
・現在は失業中だが、パート・アルバイトとして働きたい人
・働いていないが、家事も通学もしていない人で、パート・アルバイトを希望している人
※参照元:総務省統計局
このように総務省によるとフリーターは「15歳~34歳までの非正規雇用者、または非正規雇用を希望する人」ですが、一般的には年齢の上限はそこまで気にされていません。
アルバイト・パートとの違い
先ほど「フリーターはアルバイト・パートで働く人(または希望している人)」と説明しました。
しかし「アルバイト・パート=フリーター」ではなく、以下のような違いがあります。
■アルバイト・パートは「雇用形態」
「今どんな契約で働いてるか?」を表す言葉。
学生でも主婦でも高齢者でも関係なく、働き方そのものを指します。
アルバイト:学生に多い呼び方。時間の融通が利きやすい短時間労働。
パート:主婦層などに多い呼び方。家庭と両立しやすい働き方。
※企業によって明確な区別はなく、呼び方の違いにすぎないケースが多い。
■フリーターは「属性(立場)」
「どんな人がその働き方をしているか?」を指す言葉。
アルバイトやパートとして働いている“特定の若者層”に使われる。
【例】
・30代の主婦がパートで働いている → パート従業員ではあるが、フリーターではない
・大学生がアルバイトしている → アルバイトではあるが、フリーターではない(学生は含まれない)
・20代の既卒の男性がアルバイト中 → フリーターに該当する
・20代の既卒・未婚の女性がアルバイト中 → フリーターに該当する
このように「アルバイト・パート」は雇用契約の呼び方で、「フリーター」はその働き方をしている人の属性や社会的な位置づけに近いという違いがあります。
ニートとの違い
厚生労働省では、「ニート」を「15~34歳の非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者」と定義しています。
フリーターとニート、どちらも「正社員ではない若者」という点は共通していますが、ポイントは「働いているかどうか」と「働く意志があるかどうか」。
仕事をしておらず、働く意志がない(職探しもしていない)場合にニートに該当します。
フリーターでいることの何が悪い?そのリスクやデメリット
一生フリーターでいることのリスク
解雇される可能性がある
フリーターはアルバイトであり「非正規雇用」です。
この非正規という立場は、企業側にとって都合のいい雇用形態である反面、労働者側からすると「いつ切られてもおかしくない立場」でもあります。
景気が悪化したり、シフトが削減されたり、人件費が見直されたりすれば真っ先に対象になるのは正社員ではなくフリーターです。
法律的にも正社員に比べて解雇のハードルが低いため、雇用の安定性には大きな不安がつきまといます。
結婚が難しくなる可能性
フリーターという立場は、結婚というライフイベントを考える際、不利になることが多いのも事実です。
理由はシンプルで「収入や将来性に不安がある」といった印象を持たれがちだから。
たとえば、婚活市場では「正社員かどうか」が相手選びの判断基準になることもありますし、相手の親世代が「安定した職に就いているか」を気にするケースも多いです。
実際、子どもを持つことを視野に入れたとき、保育園の入園や住宅ローンなどでも、安定した収入証明が求められる場面が増えます。
もちろん、フリーターでも幸せな結婚をしている人はたくさんいます。
ただ、「一生フリーター」でいくと決めたなら、社会的なハードルを越えるための別の武器(人間力・信頼・経済的裏付けなど)が求められるということは覚えておきましょう。
年齢を重ねると転職で不利
20代のうちは、フリーターでも若さやポテンシャルでチャンスを掴めることがあります。
しかし、30代以降になると求人側は「これまでの経験やスキル」に注目するようになります。
そのため、キャリアの積み上げが少ないフリーター歴が長い人ほど、転職市場で選ばれにくくなるのが現実。
特に、異業種や未経験分野へのチャレンジは年齢が上がるほど厳しくなってきます。
また、フリーターとして働ける仕事自体も、若年層を対象にした募集が多く、年齢によるミスマッチも起こりやすくなります。
つまり、「フリーターを続けることで、将来の選択肢が減ってしまう」可能性があるということです。
老後の経済的困難
そして、深刻なのが「老後の生活費問題」。
正社員の場合は厚生年金に加入しているため、将来的に受け取れる年金額もフリーターと比べると多め。
しかし、フリーターが入るのは原則として国民年金のみ。
この差は将来、月に数万円単位の収入格差として現れます。
さらに、退職金もなければ企業年金もなし。
貯金や資産運用で老後資金を自力で積み立てなければならず、「働けなくなった後どうするか」というリアルな問題に直面するのです。
医療費、介護費、住居費など歳を重ねるほどお金はかかるにもかかわらず、十分な年金も貯蓄もないまま老後に突入するリスクが「一生フリーター」という生き方には付きまとうのです。
一生フリーターでいることのデメリット
生涯賃金が低い
まず最初に浮かぶデメリットは、一生を通して得られる収入(生涯賃金)が低くなること。
2024年に行われた厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によると、正社員・非正規社員の2023年1月~12月の賃金は以下のとおりです。
■正社員:348万6000円
■非正規社員:233万1000円
■雇用形態間の賃金格差=66.9%
《 補足 》
※正社員=元データ表記は「正社員・正職員」
※非正規社員=元データ表記は「正社員・正職員以外」
※賃金=令和5年(2023年)6月分として支払われた所定内給与額の平均額
※賃金格差(%)= 非正規社員の賃金 ÷ 正社員の賃金 × 100
正社員と非正規社員の賃金格差は、正社員の賃金を100%としたとき、「100%とどの程度差があるか」で考えられています。100%に近いほど格差が小さく、100%から遠いほど格差が大きいと言えます。
※参照元:厚生労働省┃令和6年賃金構造基本統計調査の概況┃第6-3表 雇用形態、性、産業別賃金、対前年増減率及び雇用形態間賃金格差(PDF13ページ)
正社員と比べて時給ベースの仕事が多いフリーターは、働いた時間に応じた収入しか得られず、キャリアを重ねても大きく年収が伸びることは少なめ。
ボーナス・昇給・手当などもないケースが多いため、長期で見たときの蓄財能力に大きな差が出てきます。
この差は、生活レベルや老後資金、将来の選択肢に直結するといっても過言ではありません。
「今は十分暮らせているから大丈夫」と思っても、時間が経てば経つほどその差は広がっていくのです。
社会的信用が低い
次に大きいのが「社会的信用」の話です。
クレジットカードの審査や住宅ローンの申し込み、賃貸契約、携帯電話の分割購入など「信用情報」が関わる場面では、フリーターという肩書きが不利に働くことがあります。
なぜなら、フリーターは「収入が安定していない=支払い能力に不安がある」と見なされるため。
これは実際の収入額とは関係なく「職業属性」で判断されるケースが多く、いくら真面目に働いていても評価されにくいという理不尽さがあるのです。
世間体が気になる
他人の目が気になるタイプの人にとっては「一生フリーターです」と言うこと自体にストレスを感じることもあります。
親戚付き合い、地元の友人との再会、職場外での人間関係などで「まだ正社員じゃないの?」「就職しないの?」といった言葉を投げかけられることがあるかもしれません。
本人としては自分の価値観で選んでいるつもりでも、世間の「普通」や「安定」というモノサシから外れていると判断される場面があることも事実。
このギャップが、プレッシャーや孤独感につながることもあります。
特に年齢を重ねるにつれて「自分の立場を説明する機会」や「比較される場面」が増えてくるため、フリーターという肩書きに対する自意識が強まる可能性もあるでしょう。
年金受給額が少ない
最後に、老後の年金問題。
先述したとおり、フリーターが加入するのは原則として国民年金です。
これは、正社員が加入する厚生年金に比べて受給額が圧倒的に少ないもの。
現状であれば月額5〜6万円程度が目安とされていて、家賃や生活費にあてるにはかなり厳しい金額です。
しかも、国民年金は「自分で払う制度」なので、未納期間があると将来受け取れる額がさらに減る可能性もあります。
老後に頼れる制度が少ない分、自力で老後資金を貯める必要がありますが、前述の通りフリーターは生涯賃金が少ないため、ここでも負のスパイラルが起こりやすくなるのです。
それでもフリーターでいたい!メリットと心理
フリーターでいることにもメリットがある
自分のペースで生きられる
まず大きなメリットは、自分の時間やペースを優先できること。
正社員だと就業時間はフルタイム、休みは会社都合、繁忙期には残業も…と自分の意思とは関係なく働くスタイルになりがち。
その点、フリーターなら「週3で働いて、あとは創作活動や副業に使う」「午前中だけ働いて午後は趣味に没頭する」といった生活優先型の働き方ができます。
「お金よりも自由が大事」
「好きなことを続けたいから、あえて時間を確保する」
そんな価値観にとって、フリーターは理にかなった働き方と言えるのです。
責任やプレッシャーが少ない
正社員になると、どうしても責任が増えるもの。
プロジェクトの進行管理、チームマネジメント、成果へのプレッシャー…。
人間関係のストレスや、評価されることへの疲れを感じて離職する人も少なくありません。
その点、フリーターは「任された仕事をその場でこなせばOK」という比較的軽い役割の中で働けることが多いです。
長期的な成果責任を負うことも少なく、プレッシャーやストレスを軽減できる点は大きな魅力と言って良いでしょう。
「働くことはしたいけど、精神的にすり減るのはイヤ」という人にとって、心の余白を保ちながら働けるスタイルでもあります。
働く日数や時間を選べる
フリーターの中には「働き方をコントロールしたい」という理由でこの道を選んでいる人もいます。
■家族の介護や子育てとの両立
■病気やメンタルの回復期で、フルタイムが厳しい
■夢を追うために、アルバイトを収入源にしている
こうした事情を抱える人にとって、柔軟なシフト制や短時間勤務ができるフリーターは現実的でありがたい選択肢。
「今はこの働き方しかできない」ではなく「今の自分にはこれがちょうどいい」という前向きな理由から、フリーターを選ぶ人もたくさんいるのです。
「一生フリーターでもなんとかなる」と思うその心理
アルバイトで十分稼げている
まずシンプルな理由としては「今の生活に困っていない」という実感があること。
たとえば、都心の飲食店や夜勤の工場、イベントスタッフなど時給が高めのバイトを複数掛け持ちすれば、月20万円以上の収入を得ることも可能でしょう。
「家賃も払えてるし、好きなものも買えてる」
「無理して正社員にならなくても生活できてる」
そんな実体験が「このままでもなんとかなる」という感覚につながっている、ということです。
特に貯金や将来よりも「今の自由」や「ストレスの少なさ」を重視するタイプにとっては、フリーターという働き方は十分満足できる働き方なのです。
親のサポートがある
もうひとつの大きな要素は、実家暮らしや親からの経済的支援があること。
家賃がかからず、食費や光熱費もほとんど親持ちであれば、生活コストはかなり抑えられます。
この環境があると、「収入が少なくてもやっていける」という感覚になりやすいです。
また、「いざというときは親に頼れる」という心理的な安心感も大きいもの。
結果的に「将来に備えて働かなきゃ」という危機感が薄まり、「今のままでOK」という思考が定着しやすくなります。
誰にも迷惑をかけていない
「一生フリーターでいい」と思える人の中には、自分の選択が他人に影響を与えていないことを根拠にしているケースもあります。
■生活費は自分で稼いでいる
■借金もない
■人に頼らず、迷惑をかけず、静かに暮らしている
こうした背景であれば「自立してるんだから文句言われる筋合いはない」という気持ちがあっても自然なこと。
他人の期待や価値観に縛られず、自分で選んだ人生を生きているという実感がある人ほどこのスタンスは崩れにくいです。
結婚を考えていない
「将来的に家族を持つ予定がない」という考え方も、フリーターという働き方を肯定する心理につながっています。
結婚や子育てを視野に入れると、どうしても「安定収入」や「社会的信用」が必要になるもの。
しかし、結婚願望がなく一人で生きていくつもりという前提があれば、正社員の必要性は大きく下がります。
むしろ、「一人で生きるなら、自分の好きなように働きたい」「心地いいペースを守りたい」と考えるのは自然な流れ。
そういった人にとって、フリーターは自由度の高い最適解とも言えるでしょう。
どんな人なら一生フリーターでいられる?
ミニマルに生きられる人(物欲・生活コストが少ない)
まず、物欲や生活コストが低い、いわゆる「ミニマリスト気質」の人。
フリーターの収入はどうしても安定しにくく、年齢を重ねるごとに仕事の選択肢も限られてきます。
その中で「家賃や食費をなるべく抑える」「欲しい物は本当に必要なものだけ」という生活ができる人は、収入が多少上下しても大きく困ることがありません。
身軽さ=生きやすさなので「自分に本当に必要なもの」を把握している人は強いです。
健康で、継続して働ける人
フリーターは基本的に、身体が資本。
正社員のような手厚い福利厚生や有給休暇、傷病手当がないことがほとんどなので、健康を維持できるかどうかはかなり重要です。
逆に言えば、心身ともに丈夫で体力がある人、セルフケアや体調管理が上手な人なら、年齢を重ねても自分のペースで働き続けることができます。
「健康が最大の財産」とよく言われますが、フリーターで生きていくならそれが本当に重要な意味を持ちます。
副業と掛け持ちできる人
最近は、アルバイトだけでなくフリーランスや副業、スキルを活かした業務委託など仕事を組み合わせて収入を作る人も増えています。
「ひとつの職場や業種に依存しない」「掛け持ちや副業でリスク分散できる」タイプの人は、雇用形態に依存せずとも自分の力で生活していける可能性が高いです。
自分の働き方を柔軟に変えられる人こそ、フリーターの強みを最大化できるでしょう。
経済的なセーフティネットがある人(実家・相続・支援)
実家暮らしや家族からの支援、相続など何らかの経済的セーフティネットがある人は、フリーターとして生きるハードルが下がります。
「何かあったときは実家に帰れる」「最悪、住む場所だけは確保できる」など、いざというとき頼れる場所があるかどうかはとても大きいです。
こうしたバックアップがある人は、精神的な余裕も持ちやすく、働き方の選択肢も広がります。
将来が不安なことも本音…正社員になるメリットは?
収入が安定する
正社員の一番大きなメリットは、毎月安定して給料がもらえること。
アルバイトの場合、シフトが減ったり契約が切れたりすると収入が大きく変動します。
その点、正社員は基本的に毎月同じだけの給与が入るので、家計の計画も立てやすいですし「来月どうしよう…」という心配を減らせます。
突然病気になって休んだ場合でも有給休暇や傷病手当などの制度が使えるので「働けなくなった=収入ゼロ」とはなりにくいのも安心材料です。
昇給や賞与が期待できる
正社員には、定期的な昇給やボーナス(賞与)がある場合が多いです。
年に一度の昇給や夏・冬の賞与など、働いた成果が収入に反映されるので、やる気にもつながります。
アルバイトだと時給が何年働いてもほとんど変わらなかったり、ボーナス自体がなかったりしますが、正社員なら「長く働くほど給与が上がる」という仕組みがあるのは大きな魅力です。
年収が高くなる可能性
一般的に、アルバイトよりも正社員のほうが年収は高くなります。
これは基本給が高いだけでなく、各種手当や残業代、ボーナスなども含めてトータルでの収入が上がるためです。
また、年齢や経験を重ねるほど役職がついたり、業務の幅が広がったりして、さらに収入が増えていくことも多いです。
「このままフリーターでいいのかな…と悩む理由のひとつが将来の生活費や老後資金だと思いますが、正社員なら収入面での安心感が違います。
解雇されるリスクが低い
「明日から来なくていい」といった急な解雇は、アルバイトや契約社員では珍しくありません。
その点、正社員は法律でしっかり守られているので、簡単にクビになることはありません。
会社の経営状況が悪くなっても、すぐに解雇される心配はかなり低いです。
雇用が安定するという意味で、正社員の安心感は大きいものです。
社会的信用が高まる
意外と大きいのが「社会的信用」です。
家を借りるときやローンを組むとき、携帯の分割払いなど「正社員ですか?」と聞かれる場面はかなり多いもの。
正社員の肩書きがあるだけで審査が通りやすくなったり、条件が良くなったりするのは事実です。
また、親や周囲の安心感も全然違います。
「安定して働いている」という信用は、想像以上に大きな武器になるのです。
会社によっては退職金がある
フリーターにはほとんど縁がない「退職金」ですが、正社員なら退職時にまとまったお金がもらえる会社も多いです。
これが将来の生活費や転職活動の資金、老後の備えとして役立ちます。
「働き続けた先に、ちゃんと自分に返ってくるものがある」というのは大きな安心材料。
最近は個人で老後の資金を準備する時代と言われていますが、そうなるとなおさら退職金の有無は大きいです。
フリーターから脱却するとしたら?
正社員向け求人を探して応募する
フリーターから抜け出すためのシンプルな方法は、正社員求人に応募すること。
最近は「未経験OK」「学歴不問」といった間口の広い求人も増えていて、フリーターや第二新卒を歓迎する企業も少なくありません。
求人サイトやアプリを活用すれば、希望の職種や条件で絞り込んで探せるし、スカウト機能で企業から声がかかることも。
「自分にできる仕事がなさそう」と感じている人でも、実際に検索してみると意外と選択肢はあるものです。
書類や面接でアピールする経験が少なくても、「働きたい」という意欲をしっかり伝えることで、評価してもらえる可能性は十分あります。
ハローワークの職業訓練を受けてスキルを身につける
「やりたい仕事はあるけど、スキルが足りない」という人は、ハローワークの職業訓練(公共職業訓練)を活用するのがおすすめです。
職業訓練では、パソコン操作・簿記・介護・Webデザイン・プログラミングなど実務に直結するスキルを無料または低コストで学べます。
また、訓練期間中に「職業訓練受講給付金」が支給されるケースもあるため、経済的な不安があっても挑戦しやすいのがメリットです。
「未経験から手に職をつけたい」「興味のある分野にステップアップしたい」という人にとって、スキルと自信を得られるチャンスになるはずです。
未経験歓迎が多い職種からステップアップする
「正社員になりたいけど、経験もスキルもない」と感じている人は「未経験歓迎」の職種から一歩踏み出すのもアリです。
最初の入り口として選びやすく、そこから経験を積めば、徐々にキャリアアップも目指せます。
以下のような職種は未経験者の採用に積極的な企業が多いです。
■介護職(資格支援ありの求人も多い)
■飲食・接客業(ホールスタッフ、販売員など)
■コールセンター(マニュアル完備&研修あり)
■配送ドライバー・倉庫作業(体力がある人におすすめ)
■工場・製造業(軽作業、ライン作業など)
中でも「工場勤務」は、学歴や職歴よりもまじめにコツコツ取り組む姿勢が評価される職場が多いのが特徴。
正社員登用制度がある企業であれば、アルバイトや派遣社員からスタートして、ステップアップしてから正社員になれる可能性があります。
働きながら「フォークリフト」や「玉掛」といった専門資格を取得することで、よりキャリアと収入アップを狙えるのもメリットです。
未経験歓迎求人多数!製造業・工場特化のHOPEエージェント
「一生フリーターは不安だけど、最初から正社員として働くのもしんどい」
そんなときは正社員にこだわりすぎず、派遣を「つなぎ」にするのもひとつの手。
製造業や工場系の仕事には、未経験・フリーター歓迎など入口が広い求人が多数。
まずは派遣で現場経験を積んでから、ゆくゆくは正社員登用につながるケースも少なくありません。
「働きながらスキルをつけたい」「いきなり正社員はちょっと不安」という人におすすめしたい選択肢です。
そこで心強い味方になってくれるのが、製造業・工場に特化した人材エージェント『HOPE.AGENT』。
\ HOPE.AGENTの特徴 /
◎ 取り扱い求人は製造業に特化、常時1,000件以上!
◎ 専属エージェントがワンストップサポート(相談、求人紹介、履歴書の添削・面接対策・キャリアチェンジまで)
◎ 年間800人以上をサポートしてきた実績あり
◎ 身だしなみや言葉遣い、ビジネスマナーのレクチャーあり
◎ 仕事内容が合わなかった場合は、別のお仕事をご案内可能
HOPE.AGENTは「求人を紹介して終わり」ではありません。
身だしなみや言葉遣いといった社会人スキルの底上げ、ワンストップの就職サポートなど徹底したフォローに自信があります。
職歴が浅い、未経験、異業種からのチャレンジなど様々な背景を持った方たちの人生に向き合ってきました。
新しい一歩を踏み出すときに感じる不安や迷い、そんな気持ちはぜひHOPE.AGENTへご相談ください。
★━━━━━━━━━━━━━━…
…━━━━━━━━━━━━━━━━★
まとめ
・フリーターの定義や立場は、「働き方」ではなく「属性」によって決まる
・一生フリーターでいる場合、収入・信用・老後の不安といったリスクが現実的にある
・その一方で、自由な働き方・責任の軽さ・生活との両立といったメリットもある
・「なんとかなる」と感じる人には、親のサポートや結婚願望のなさなど心理的背景も
・フリーターを続けられる人の共通点は「ミニマルな生活・健康・副業力・セーフティネット」
・将来に不安を感じたら、正社員になるメリットやステップアップ方法も視野に入れよう
・「どちらが正しいか」ではなく、「どんな人生を選ぶか」が大切な時代だからこそ、自分の選択を見つめ直してみよう
・不安や悩みは一人で抱え込まず、求人エージェントなどのプロにも気軽に相談を!